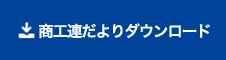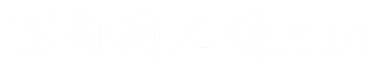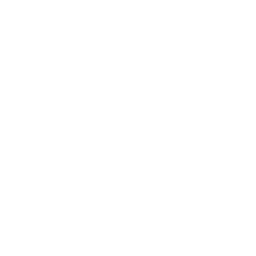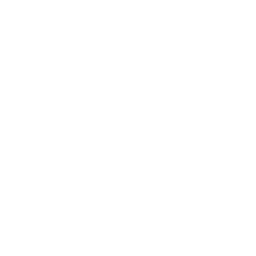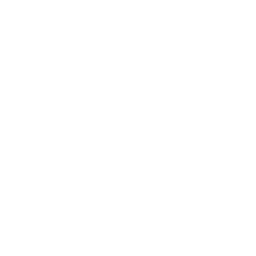現代の感性を反映させ、未来に生きる日本刀作りに挑む。


日本刀の製造工程

日本刀が生み出される鍛冶場

製作した短刀

日本刀の「美」をレジンに封じ込めた作品
名工の下で修業した刀鍛冶が京丹後に鍛冶場を開く
京丹後市で日本刀を製作・販売する株式会社日本玄承社。刀鍛冶の国家資格を持つ3人の刀匠が2019年に会社を設立し、2022年1月、鍛冶場を開いた。
現在の刀職の最高位といわれる「無
鑑
査
刀匠
」の称号を持つ名工の下で修業を積んだ黒本知輝さん、山
副
公
輔
さん、宮
城
朋
幸
さん。志を同じくする3人が、独立を機に「共にやっていこう」と決意し、起業に至った。
修業した東京ではなく、京丹後に目を向けたきっかけは、鍛冶場となる場所を探していた時、同地にある山副さんの祖父母の家が空き家になっていると知ったことだった。「訪れてみると、この地には古墳時代から製鉄所があり、刀にまつわる伝承が残っていることもわかり、不思議な縁を感じました。何より地域の方々が温かく応援してくださったことが大きかった。『ここしかない』と、3人で決断しました」と代表取締役の黒本さんは明かす。
現代ならではの感性を生かした日本刀を目指す
日本刀は、れっきとした武器でありながら、現代では美術品としてもその価値が高く評価されている。同社への注文のほとんどは個人から。居合道などの武術用の他、鑑賞・コレクション用、贈り物や家宝として求められることが多い。日本の文化や日本刀に魅せられた外国人からの注文も増えているという。
『折れず、曲がらず、よく切れる』が、日本刀の3原則です。これを徹底的に突き詰めることで立ち現れてくる機能美としての美しさ、それが日本刀の魅力です」と黒本さん。同社では、顧客の体格や好みなどを聞いて、刀の姿形や刃紋・地
鉄
の模様などを決め、一人ひとりに合わせた唯一無二の日本刀を製作する。「大切にしているのは、お客さまの『思い』を反映させることです。生年月日や好きな言葉、日本刀を求める理由などをお聞きして、それをいかに表現するかを考えます」と言う。
黒本さんらは、名刀といわれる既存の刀を模すのではなく、「未来につながる新しい刀づくり」に情熱を燃やす。「例えばアルプスの山々や音楽のデジタル波形など、昔の人は決して見聞きしなかった情報を現代の私たちは得ることができます。そうしたその時代に培われた感性や知識を反映させ、今を生きる自分たちだからこそできる刀を作りたいと考えています」
経験不足の経営面を商工会がサポート
同社が京丹後市に拠点を置いた時から支援してきたのが、京丹後市商工会だ。「職人の私たちは、経営についてはわからないことばかりです。困ったことがあると、すぐに相談し、お世話になっています」
とりわけ補助金の紹介や申請支援は、大きな助けになっているという。「補助金を活用したおかげで、事業所の照明や空調機器などを購入し、環境を整えることができました。現在は、観光客向けの鍛冶場見学や刀鍛冶体験に関わる新たな設備の導入を考えており、それも支援していただいています」
京丹後に根を下ろした今、地域企業とのつながりも広がっている。螺
鈿
織
の織物会社や精密加工業者と協業し、日本刀の装飾や金具を作るなど、異業種連携にも取り組む。
今後は、地元産の原材料を用いて、「京丹後産の日本刀」を作ることが目標の一つだという黒本さん。古代製鉄文化が栄えた地で、未来につながる刀作りに挑戦していく。
7年間の修業を経て刀鍛冶として独立
刀鍛冶は、望めば容易になれるわけではない。文化庁から承認された刀鍛冶の下で5年以上修業し、さらには文化庁が主催する「美術剣刀匠技術保存研修会」を修了して初めて、刀鍛冶として日本刀を製造することが許される。
大阪出身の黒本さんは、高校卒業後、単身上京して「無鑑査刀匠」の吉原義人(よしんど)氏に直談判して弟子になった。義人氏と息子の義一氏に学びながら腕を磨き、刀鍛冶の資格を取得。約7年の修業期間を経て独立した。
修業場は東京都葛飾区にあり、黒本さんにとって京丹後は見ず知らずの場所だったが、今ではこの地域に深い縁を感じている。
「鍛冶場の近くには、鬼退治伝説が残る麻呂子(まろこ)皇子が、鬼を切った刀を奉納したという言い伝えが残る竹野(たかの)神社があります。何より驚いたのは、遠い昔、この地域に古代製鉄所があったと知ったことです」
京丹後市にある「遠
處
遺跡製鉄工房跡」は、6世紀から8世紀頃にかけて営まれていた製鉄所の跡。ここでは製鉄から鍛錬、完成品まで、一貫生産されていたことがわかっている。千数百年前に、黒本さんらと同じ生業を営んでいた人々がいたということだ。そうした古代の鍛冶職人たちに思いを馳せながら、黒本さんらは師匠に鍛えられた伝統的な製法を守り、刀作りを続けている。
京丹後の伝統産業と連携し、新たな日本刀を追求
刀鍛冶の技が光る日本刀の見どころは、主に三つある。一つは、その姿。長さや厚み、反り具合は、使う人の体型や使用目的によって実にさまざまだ。二つ目には、刃紋だ。焼き入れ工程でつけられる白い波のような紋様のことで、丁
子
、重
花
丁
子
、
直刃
、互の目、湾
れなど、数多くの種類がある。「時代や作り手によって、流行や得意な刃紋があります。当社では、丁子が多いですね」と言う。
そして最後が、地鉄
といわれる刀身の濃い色の部分だ。一見すると、濃い灰色一色のようだが、目を凝らすと、細かな肌模様が見える。高純度の玉鋼を高熱で叩いては折り返す「折り返し鍛錬」によって現れるもので、刀鍛冶の技や丹精な仕事ぶりが見て取れる。
現代ならではの感性で、時代に求められる刀作りを目指す黒本さん。「例えば、デジタル音楽の波形など、昔の人は見たことのない模様を刃紋に入れるのも、面白いかもしれません」と、想像を豊かに広げ、新しい日本刀の表現を追求している。
また地域の異業種連携にも意欲的だ。京丹後エリアには、織物業や金属加工業の企業が数多くある。「当社の近隣にも、螺鈿織を手がける織物会社があります。螺鈿を織り込む螺鈿織は、西陣織の帯地などに使われる伝統の技の一つです。こうした会社に協力を仰ぎ、これまでにない螺鈿織の『拵
え』(日本刀の外装)を作ってみたい」と言う。
また日本刀は、刀身だけでなく、鍔
や
笄
など、数々の部品をつけて完成する。「高度な金属加工技術を持つ企業と連携し、現代ならではのデザイン性の高い部品や装飾を一緒に作っていけたらと考えています」と期待を膨らませる。
次世代を担う刀鍛冶の育成にも注力したい
「いずれは次代の刀作りを担っていく人を育てることにも力を注ぎたい」と、黒本さん。未来に日本刀やその産業を残していくことへの思いは、ひと際強い。「そのためには、事業を大きくし、人材を雇用できるだけの利益をあげなければならないと考えています」と、売上拡大の努力も惜しまない。というのも、刀鍛冶が減少している背景には、経済的自立が難しい構造があると考えているからだ。
「私の修業時代は、基本的に無給で、師匠の仕事を手伝いながら学ぶ生活。住居費や生活費は、休日にアルバイトをして賄いました。そんな生活では、独立資金を貯めることもできないし、社会的信用を得ることもままなりません。刀鍛冶の資格を得たとしても、独り立ちするのは、簡単ではありません」
黒本さんらが株式会社を設立したのも、こうした現状を打破し、若い刀鍛冶が給与を得ながら仕事を続けていける環境をつくりたいと考えたからだ。
会社と刀鍛冶の知名度を高めるため、鍛冶場を公開して観光客などを受け入れ、鍛冶場見学や小刀製作体験といったプログラムも提供する。
現代ならではの経営で、伝統の技と担い手の継承にも貢献していく。